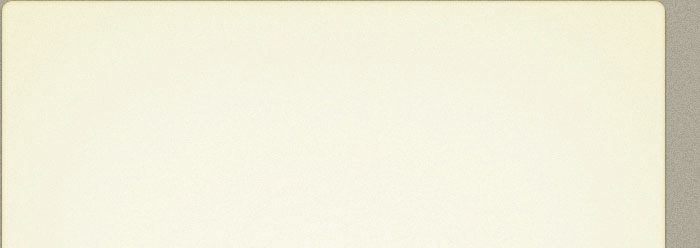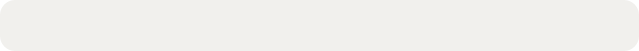破産(手続)という言葉は,テレビや新聞でもよく聞かれると思います。
その意味として,個人については支払えなくなった債務を法律的に免除してもらう手続であり,会社については債務を清算して解散する手続というように認識されている場合が多いと思います。
大まかな理解としては誤りではありませんが,元々,破産手続というのは債権回収手段のひとつでした。
債権回収のために行われる差押などの強制執行手続は,原則として早い者勝ちです。以前ご説明しましたが,差押の対象になる財産にはお金に換えやすい物と換えにくい物がありますが,早く差押えをすれば,お金に換えやすい財産を差し押さえることが可能です。
しかし,このような早い者勝ちは,債務者にすべての債務を支払うだけの資産がない場合には不公平な結果になってしまいます。
本来,破産手続というのは,そういう場合に債権者による個別の強制執行を禁止して,裁判所が選任した破産管財人が債務者のすべての資産をお金に換えて,債権者に公平に分配するための手続でした。
そのため元々は債権者が申し立てる場合の方が多かったのです。
しかし,このやり方が上手くいくためには,債務者にある程度の資産が残っている状態で破産手続が始まる必要がありますが,多少なりとも資産がある状態で債権者から破産を申し立てられた債務者は,その債権者にだけ弁済して破産申立を取り下げてもらい,結局,資産がなくなるまで営業を継続することが多いのです。
その結果,実際に破産宣告がされたときには資産が残っていないことになります。
私が弁護士になった約30年位前に債権者による破産申立と債務者自身による破産申立がほぼ同数になり,その後,ほとんどが債務者自身による破産申立になっていきました。
現在では,ある程度の資産が残っているが経営が困難であるという債務者は,民事再生などの手続で再建を図る場合がほとんどです。