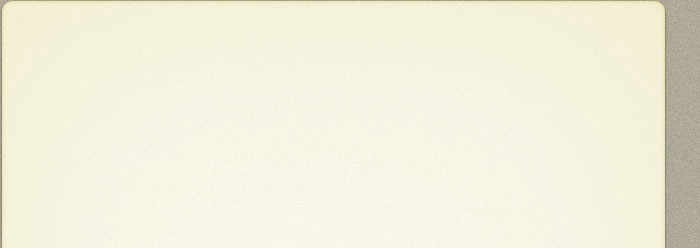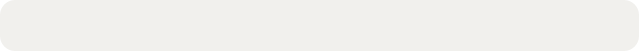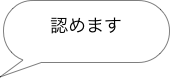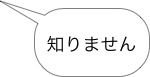今回は民事裁判の審理について簡単に説明します。
原告が裁判所に訴状を出し,被告が請求の棄却を求めて事実関係を争うと,争われた点についての審理が始まります。
前回,原告が主張しなければならない請求の原因になる事実は,請求の内容ごとに決まっていると説明しました。
どういう請求をするときに,どういう事実を主張しなければならないか,という点は,とても専門的な話になりますが,例えば,貸したお金を返してもらいたいときは,お金を渡した事実と返すという約束をした事実を主張することが必要です。
お金を渡したことだけを主張しても,そのお金を贈与しただけかも知れないからです。
従って,貸したお金を返せという裁判で,お金を渡したことだけを主張しても,請求が認められることはありません。
必要な事実が,すべて主張されると,被告は,ひとつずつ,認める,認めない(「否認」と言います),知らない(「不知(ふち)」と言います)という回答をすることになります。
例えば,お金は受け取ったが,返す約束はしていない(つまり,もらった)という答弁がされたとします。
すると,お金を渡した事実については,争いがないことになり,裁判所は,その点について,その後,審理はしませんし,実はお金は渡っていないというような判断をすることも禁止されます。
審理の対象は,お金を返す約束の有無だけになり,原告がそれを立証できるかどうかが問題になります。
日本の民事裁判では,原則として立証の方法に制限はありませんので,契約書などの書面で立証しても,証人を呼んで立証しても,両方とも使って立証しても差支えはありません。
立証の結果,裁判官が10中8,9間違いがないと感じた場合,その事実の存在を前提にした判決になり,その程度に届かない場合は,その事実はないという前提の判決になります。