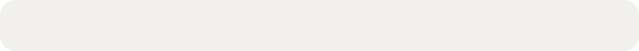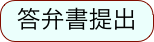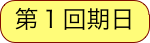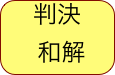前回は,民事裁判と刑事裁判の2種類の区別について,説明しました。
今回は,まず民事裁判の仕組について簡単に説明したいと思います。
民事裁判は,訴えを起こしたいと思った人が,裁判所に訴状を提出することが最初の一歩です。
裁判所は,訴状が提出されると,形式的な不備がないかを審査して,問題がなければ,原告と第1回期日をいつにするかの打合せをして決め,訴状と期日の呼出状を被告に郵送します。
訴状を受け取った被告は,指定された第1回期日までに裁判所に「請求を棄却する」と書いた答弁書を提出するか,第1回期日に出頭して,法廷で「請求を棄却する」と答弁しないと,無条件で敗訴になります。
これは,仮に原告の訴えの内容が間違っていても,負けになってしまうので気をつける必要があります。
裁判所からの連絡文書には,答弁書の提出期限として第1回期日の1週間前までと書かれていますが,期日までに提出すれば無条件で敗訴になることはありません。
また,第1回期日の日程は,被告の都合を聞かずに決めますので,「請求を棄却する」と書いた答弁書さえ提出しておけば,出頭の必要はありません(これを擬制陳述と言います)。
次に被告としては,原告が主張する請求の原因になる事実について,ひとつずつ,認める,認めない(「否認」と言います),知らない(「不知(ふち)」と言います)という回答をすることになります。
ただし,原告が主張しなければならない請求の原因になる事実は,請求の内容ごとに決まっています。
被告が請求の棄却を求めた裁判で,原告が必要な事実を主張していないと,それだけで原告の側が負けてしまいます。
もちろん裁判所から,必要な事実が抜けていませんか?という問いかけ(「釈明」と言います)は,ありますが,裁判を弁護士に依頼した方が良い理由のひとつは,この点にあります。