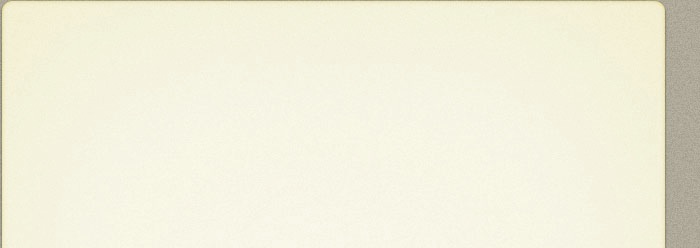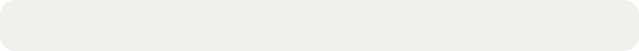今回は民事裁判における和解手続について説明します。
前回は,判決を前提とした民事裁判の審理の方法についてご説明しました。
しかし,実際の裁判では,多くの場合,判決に至らず,和解という手続で審理が終了します。
これは,裁判手続の中で原告と被告がある程度,譲り合い,合意に至った場合,その内容で解決をする手続です。
その意味では,裁判外での示談交渉に似ていますが,いくつかの違いがあります。
ひとつは効力です。
裁判で成立した和解は,和解調書という裁判所が作成する書面が作成されることによって,確定した判決と同じ効力があります。
従って,和解で決めたことが守られない場合,強制執行をして強制的に権利を実現できます。
一般の示談契約では,約束が守られない場合,改めて裁判をしなければ強制執行はできません。
公正証書を作成すれば,金銭支払だけは強制執行ができるようになりますが,公正証書では,物の引渡や家屋,土地明渡などの強制執行はできません。
裁判所の和解ではこのようなことも可能です。
もうひとつの違いは,裁判の審理をしている裁判官が中に入るため,当事者が譲歩しやすいという点があります。
当事者が,裁判所の和解案に不満で納得できない場合,和解は成立せず判決が出されることになります。
しかし,その判決を出すのは,和解案を提案した裁判官です。
和解のときに,どの程度,判決の内容を前提にするかは,和解手続の時期のほか,裁判官の考え方にもよりますので,和解案の内容が必ずしも判決とほぼ同じというわけではありませんが,逆にあまりにも違うことも問題があるとされています。
そのため,裁判所の和解案に従った方が無難だと考える当事者が多く,訴訟外の示談よりも成立しやすいのです。