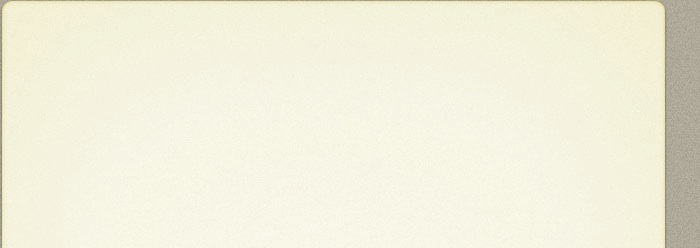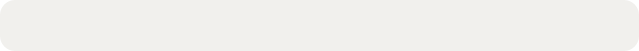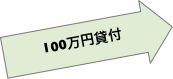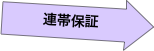お金を借りるときや家を借りるときなどに保証人を立てることを求められる場合があります。
法律番組などでは,普通の保証人と連帯保証人の違いについて説明されます。ごく大雑把に言えば,そのような番組の結論は,連帯保証人はただの保証人よりも極めて責任が重いので,注意が必要であるということになります。
しかし,現実の取引において,連帯保証人ではない,ただの保証人で良い場合と言うのは存在しないと言っても過言ではありません。
従って,実際には「保証人」と「連帯保証人」の選択肢があるわけではありません。連帯保証人になるかならないか,連帯保証人が必要な取引をするかしないか,という選択肢しかありません。
連帯保証人になると,本人が支払を怠ったときは,全額直ちに請求されます。本人に請求してくれとか,本人の財産を確認してくれとは言えません。また,連帯保証人がふたり以上いても,全員が全額の請求を受けます。
例えばXからYが100万円を借りるときにAとBが連帯保証人になったとします。
全く返済がなくて裁判になったときの判決は,「被告ら(Y,A,Bのことです)は,連帯してXに対し,金100万円及び,これに対する平成○○年○○月○○日から上記支払済まで年○分の割合による金員を支払え」などとなります(後半は前回ご説明した遅延損害金の支払を命じる部分です)。
以前はこの判決は「被告らは,各自,Xに対し,(以下同)」と書かれていて,法的知識のない人からは,100万円しか貸していないのに300万円の支払を命じるのか?などという誤解がありました。
もちろん,Xが元本として受け取れるのは100万円が限度です。しかし,Y,A,Bの誰から,いくらずつ受け取っても良いのです(例えばBだけから100万円支払ってもらっても構いません)。
そのためには,全員が100万円の支払義務を負い,誰かが実際に支払った場合にだけ,支払義務の範囲が減少する(これは当然のことで判決には書かれません)という扱いが必要だということです。