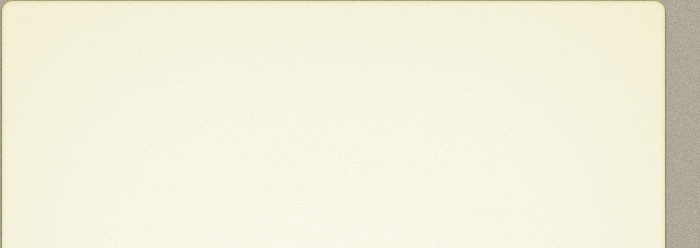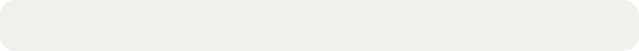民法という法律があり,様々な取引に関する規定や身分関係,相続関係などについて規定されています。
取引に関する規定は,主に第3編債権というところに書かれています。
ちなみに第1編「総則」は,取引の前提になる規定が書かれており,第2編「物権」は,取引の対象の内,物権の内容が規定されています。
第4編は「親族」,第5編は「相続」です。
第3編「債権」には,契約という章があり,贈与,売買など13種類の契約について規定されています。
そこには,それぞれの契約の内容が規定されていますが,実はこれらの規定のほとんどは,従う必要がない規定であり,任意規定と呼ばれます。その逆は強行規定と呼ばれ,民法でも債権法以外の部分は,ほとんどが当事者で勝手に変更することはできません。
「契約自由の原則」という言葉をご存じでしょうか?
近代法は,当事者がどのような内容の契約を結ぶことも原則として自由であるという考え方の上に成り立っています。
つまり,契約を結ぶときに,民法にこう書いてあるから,この通りの条項にしないといけないということはないのです。
それでは,これらの民法の債権法の規定は,何のためにあるのでしょうか?
当事者が自由に契約の内容を決めても良いとしても,素人同士の契約では,想定外の状況について,きちんと規定できていない場合があり得ます。
また,規定の文章があいまいで,意味が確定できない場合もあり得ます。
そのようなときに足りない部分を補ったり,不明確な部分の解釈の基準となるのが,民法の規定なのです。
しかし,民法が契約自由の原則の適用対象として想定するのは,対等な立場の当事者です。
例えば,事業者と消費者という関係であると,契約自由の原則をそのまま適用するのが不適切な場合が出てきます。
この点については,次回にご説明します。