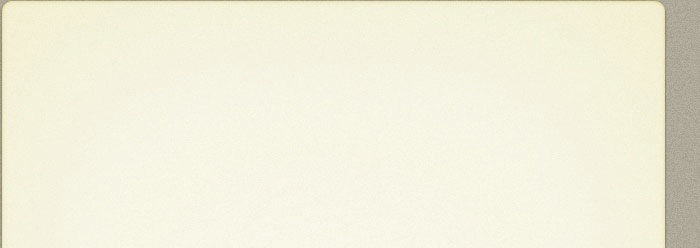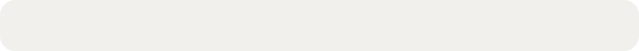前回は契約自由の原則を前提として,民法の債権に関する規定は,ほとんどが従う必要がない任意規定であるということを説明しました。
しかし,現在では事業者と消費者の間の契約では,この原則が修正されています。
今回は,このことについて説明をします。
契約自由の原則は,契約の各当事者が対等の関係であることを前提にしています。
例えば業者間の契約や,一般の人同士の契約です。
ところが,業者と一般の人,つまり消費者の間の取引については,契約自由の原則を貫くと問題があります。
業者はその商品や取引の内容について,豊富な知識を有していますが,消費者は一般的には知識がありません。
その結果,契約の内容を自由に決められるとすると,業者が自分に有利な内容で契約を結ぼうとしていても,消費者にはそれが分からず,予想外の損害を被る可能性があります。
そこで平成13年4月1日に施行された消費者契約法は,以下の規定を置きました。
「民法 、商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。」(10条)
また8条には事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効について,9条には消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効についての規定があります。
これらの規定は,本来,契約から漏れていた部分を補充するだけの意味しかなかった民法の任意規定を消費者保護の最低ラインとして使用するものです。
民法の規定は,その契約について,一般的な人が有するイメージにだいたい沿った内容になっていますので,その期待を裏切らないようになっているわけです。