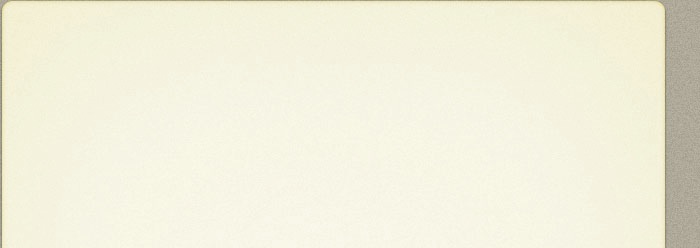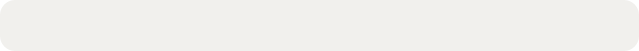今回は刑事裁判のしくみについて説明します。
以前にも少しご説明したことがありますが,刑事裁判は民事裁判とは違った点があります。
まず,裁判を起こすことができるのが検察官に限られています。
次に証拠の提出は,まず検察官が行いますが,書面による証拠は原則として弁護人が同意したものしか提出できません。
そのために検察官は,事前に弁護人に対して提出予定の書面を見せなければなりません。
この手続は,刑事裁判は,法廷で裁判官が,直接,人から話を聞くことを原則とし,書面で代用することを,例外にするという考え方から来ています。
例えば,目撃者が目撃状況について嘘の書面を書いても,書面に対して不審な点を質問することはできません。
法廷に目撃者本人を呼べば,納得できない点などを直接,確かめることができます。
このような考え方に基づいた手続ですので,不動産登記簿や戸籍など,初めから書面でも問題がないものは弁護人の同意は不要です。
また,記載内容に争いがなければ,弁護人も同意しますので,法廷で証拠として取り調べられます。
弁護人が同意しなかった書面は,原則として検察官が取調べの請求を撤回し,必要があれば証人尋問などを請求することになります。
原則に戻って,直接,話を聞くということです。
被告人自身が事実関係を認めている場合でも,民事事件とは違って,一応,証拠の取調べは行われます。
刑事事件では,被告人の自白だけで有罪とすることはできないからです。
また違法に収集された証拠も裁判の資料にはできませんので,裁判官はそれを見てしまった後でも,見なかったものとして判決を出すことになります。
そのようなことが可能なのかという疑問もありますが,裁判所は,裁判官は職業上の技術として,そういう考え方ができるのだと言っています。