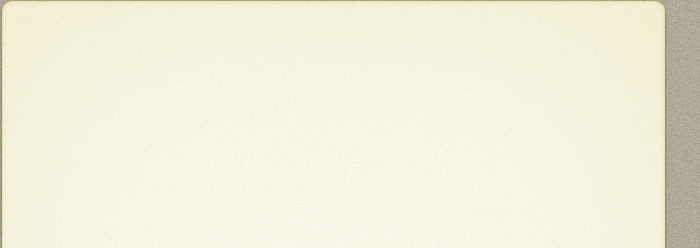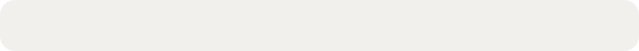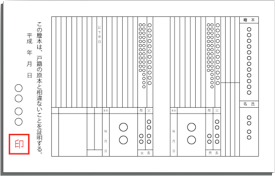今回は意外に誤解が多い戸籍のしくみついて説明します。
戸籍を意識するのは,人の誕生と死亡の他では結婚と離婚の場合だと思います。
結婚に関しては,嫁入りするとか,婿養子になるというような言い方をされる場合があり,日常用語としては目くじらを立てる必要はないと思いますが,法律的にもその言葉と同じような効果があると誤解されている方がかなりいらっしゃいます。
現在の親族の制度やそれを記録する戸籍の制度は,戦後,大きく変わりました。
誤解が生じる理由は,戦前の家制度の発想が現在でも残っているためだと思います。
しかし,現在の親族制度と戸籍制度は,少なくとも建前上は,そのような発想と全く違う仕組になっています。
現在の戸籍は,夫婦とその子というパターンを最大限の形としており,3代以上(つまり祖父母や孫)が同じ戸籍に入ることがありません。
そのため結婚をする場合には,既に単独の戸籍になっている場合を除き,夫も妻もその親の戸籍から出て新しい夫婦の戸籍が作られます。
従って,夫婦のどちらかが,その親の戸籍に入ることはありません。
その上で,夫婦別姓や新姓が認められないため,どちらの姓を名乗るかについては二者択一になります。
従って,どちらの姓を選択してもそれは夫婦の姓でしかなく,その姓を名乗る親と特別な関係が発生するわけではありません。
一番よくある誤解は,妻の姓を名乗ることによって婿になったという誤解です。
婿という制度はありませんし,妻の姓を名乗っても,妻の両親の財産を相続する権利が発生するわけではありません。妻が夫の姓を名乗っても夫の両親の財産を相続できないのと同じです。
妻の姓を名乗るとともに,妻の両親の養子になれば相続権が発生しますが,それは養子縁組の効果に過ぎません。