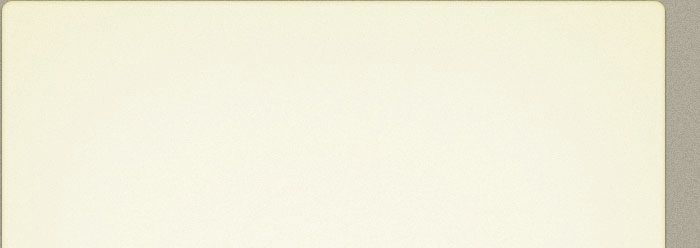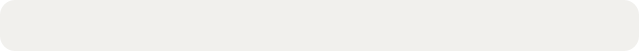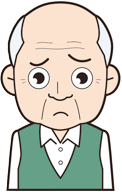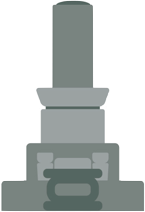前回,現在の戸籍は,夫婦とその子というパターンを最大限の形としていると説明しました。
なぜ,最大限の形という表現をしたかと言いますと,子は結婚によって親の戸籍を出るほか,成年に達した子は,結婚しなくても分籍という手続で自分を筆頭者にした戸籍を自由に作ることができるからです。
しかし,分籍の手続には特に法律的な効果はありません。
法律相談で,ときどき,親と縁を切りたい,子と縁を切りたいという相談があります。
戸籍を別にしたいだけなら分籍という手続がありますという説明をすると大喜びされる方もいらっしゃるのですが,この手続によって親族間の扶養義務や相続権に影響がでることは一切ありません。
現在の法律で親子関係を終了させることが可能なのは養子縁組の解消だけです(もちろん,これも全く自由にできるというわけではありません)。
また,最近話題になっているのが,姻族関係終了届という手続であり,死後離婚などとも言われます。
姻族関係というのは,結婚によって発生する配偶者の血族(配偶者の親や兄弟など)との関係のことです。
法律関係としての夫婦関係は,離婚又は配偶者の死亡で終了しますが,離婚の場合は,姻族関係も自動的に終了します。
一方,配偶者が死亡した場合は,姻族関係は当然には終了しませんが,姻族関係終了の届出をすることで終了します。
この面について言えば,離婚と同じような結果になるため死後離婚などと言われるのだと思います。
この届出は,生存配偶者の意思で自由にできます。何の要件も必要ありません。
このような届出をするのは,死亡した配偶者(主に夫)の親族(主に親,兄弟)と関係が良好ではないとか,夫と同じ墓に入りたくないなどの場合が多いようです。
姻族関係終了届の法的な効果については,次回,もう少し詳しく説明します。