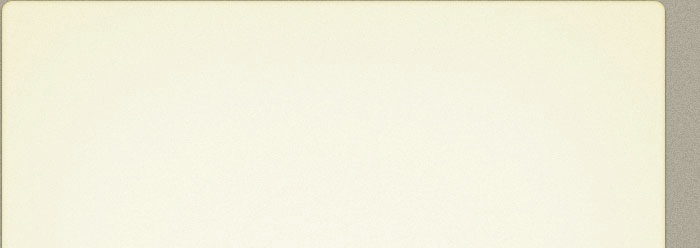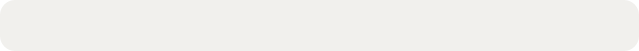前回,保険契約の特徴は,保険金の支払理由になる事故などが発生する確率が分かっていることだとご説明しました。
今回はこの点について,少し詳しく説明したいと思います。
例えば,1000軒の家がある街で,平均年1回火事があり,損害が平均1000万円である場合,毎年1軒から1万円(保険料)ずつ徴収すれば,火事に遭った家に損害をまかなうお金(保険金)を払うことができます。
また,50歳の人1000人の内,平均してひとりが1年間の内に亡くなるとした場合,1000人から1万円(保険料)ずつ集めれば亡くなった人(被保険者)の家族 に1000万円(保険金)を渡すことができます。
この場合,2000万円(保険金)を渡したければ2万円(保険料)ずつ集めれば良いのですが,最初の例の場合,渡せるお金は実際の損害額に限られます。
2万円ずつ集めて1000万円の家が燃えた人に2000万円を渡すということはできません。
それでは損害額を超えた分は,賭博になってしまうからです。
同様に損害を被らない人が,保険金を受け取る契約も許されません。
一方,2番目の例では,損害額という考え方ではありませんので,基本的には自由に金額を設定できます。
しかし,保険料を払う人(契約者)が自分以外の人が死んだ場合の契約をするときは,その被保険者(その人が死んだときに保険金が支払われる人)の承諾が必要とされます。
いずれにしても,このような契約が成り立つためには,火事や死亡などの事故が起こる確率が分かっていることが必要で,これを大数の法則と言います。
実際には,社会では様々な出来事に対して統計が取られていて,それに基づいて様々な保険が運営されています。
ここで説明した方法で計算される保険料は純保険料と呼ばれますが,実際には保険会社がここに経費や自社の利益を付加した金額を決めており,これは営業保険料と言われます。