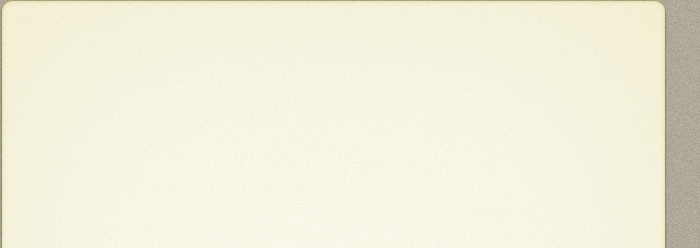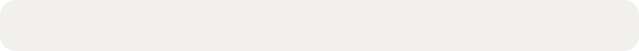私たちは,社会生活の中で他人の行為によって何らかの損害を被ることがありますし,他人に損害を与えてしまうこともあります。
法律のかなりの部分は,当事者同士でこの損害を回復するためのルールとして定められています。
損害賠償の一番原則的な規定は,民法417条であり,原則として金銭によって額を決めることになっています。
買った物が引き渡されないというような場合は,売買契約に基づいて買ったものの引渡を請求できますし,裁判によって強制的に取り上げることもできますが,これは,物の引渡については,まだ損害賠償の段階まで行っていない状態です。
代わりのない商品を他に売ってしまったなどの理由で引渡ができなくなれば,金銭による損害賠償を請求することになります。
また,契約によらずに損害賠償が問題になるのは,事故などの加害行為による場合がありますが,これも金銭による損害賠償が原則になります(民法722条1項)。
例えば,交通事故で新車が廃車になったからといって代わりの新車の引渡を請求する権利はありません(当事者で合意することは自由です)。
例外的に名誉毀損について名誉回復手段を請求できる(民法723条)という規定がありますが,これは謝罪広告などを出させる権利です。
ただこれも相手が応じなければ,被害者が加害者の名前で自分宛の謝罪広告を出して,その費用を相手方に請求することになりますので,最終的には金銭解決ということになります。
損害賠償についてもうひとつの原則は,原因になった事実と因果関係がある損害がすべて含まれる訳ではなく,通常発生する範囲の損害に限られるという点です。
そうしないと,「風が吹けば桶屋が儲かる」式に損害賠償の範囲が際限なく広がってしまうからです。
しかし,この点は,加害者と被害者で感じ方に差があることが当然であり,多くの場合,裁判で大きな争点になります。