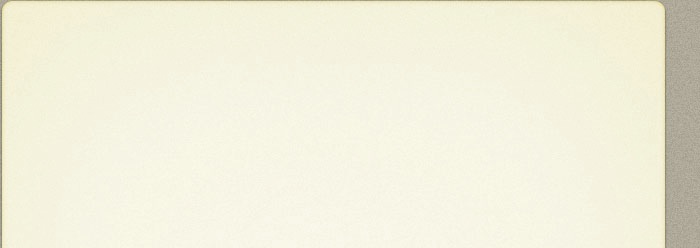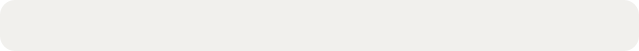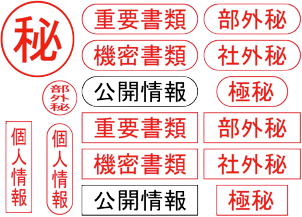これまで知的財産権の内で,特許権や商標権のように登録を前提として公開されるものについて紹介してきました。
そして,権利が登録されることのメリットを説明しましたが,発明や技術がすべて公開されているものだというわけではありません。
当然のことですが,公開された技術は独占することはできません。
誰にも使用を許諾しなければ,法的には独占可能ですが,内容を研究されることによって,それを超える技術を作られる可能性はあります。
そこで,秘密にしておけば第三者が独自に思いついたり,製品から解析することも不可能だろうという技術については,あえて特許や実用新案の登録をせず,秘密のままにしておくこともあります。
実際には,技術の中心的な部分を特許申請し,周辺の実務的なノウ・ハウ部分は営業秘密にすることが多いようです。
これによって,他社から特許料を受け取って特許を使用させても,自社の製品には性能が及ばないという状況にすることができます。
ところで,登録制度のない営業秘密には法律的な保護はないのでしょうか。
営業秘密には登録制度がありませんから,例え後からでも自力で同じ技術を開発した人には何も言えません(特許などの場合は,特許の内容を知らずに自力で開発しても,特許申請よりも後であれば特許権の侵害になります)。
しかし,秘密を盗み出したというような場合は不正競争防止法によって損害賠償請求ができますし,悪質な場合には刑事罰もあります。
公開を原則とする民事訴訟手続の中では,営業秘密が裁判手続の中で明らかになってしまわないような手当もされています。
ただし,そのためには,その営業秘密が有用なものであることや公然と知られていないことの他に,秘密としてきちんと管理されていることが必要です。
厳重に保管することの他,社内で取扱規程や管理責任者を決めたり,従業員と秘密保持契約を締結することが有用です。