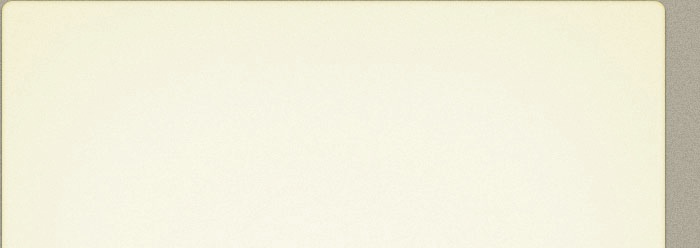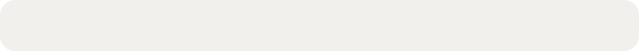事務所便り22号から28号までで,民事裁判と刑事裁判の違いを説明しましたが,テレビや新聞,インターネット上の記事などを見ていても,やはり世間一般では民事事件と刑事事件の違いや関係について,さまざまな誤解があるようです。
手続の違いについては,上記の記事をご参照頂くことにして,今回からは民事事件と刑事事件で似ている言葉の意味について説明致します。
民法には詐欺という言葉があり,刑法には詐欺罪という犯罪が規定されています。
民法96条1項には「詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。」と規定されています。
強迫については後述しますが,ここでいう詐欺とは,相手をだまして勘違いをさせることです。
ただ,その効果については意思表示を取り消すことができるというものですから,その詐欺によって意思表示がなされなければ,民事上は詐欺としての意味がありません。
意思表示というのは,法律効果に結びつく内心の決定を法律効果の及ぶ相手に表示することですが,簡単に言えば契約を結ぶとか,契約を解除するというようなことです。
ですから,騙されて売買契約を結んだような場合は,契約を取り消して,やっぱり買いませんと言えるということです。
代金を払っていれば返してもらえますし,商品を受け取っていれば返す必要があるのが原則です。
一方,刑法246条の詐欺罪は,人を欺いて財物を交付させる行為を処罰の対象にしています。
財物の交付については,意思表示にあたる場合もありますが,占有を奪うことに重点がありますので,意思表示に当たらなくても犯罪は成立します。
例えば誤って釣り銭を多く渡されたことに気づいていたのに黙って受け取るような場合です。
このような場合,多く渡した分を返して貰うために民法の詐欺による取消しを主張する必要はありません。
次回,もう少し詳しくご説明します。