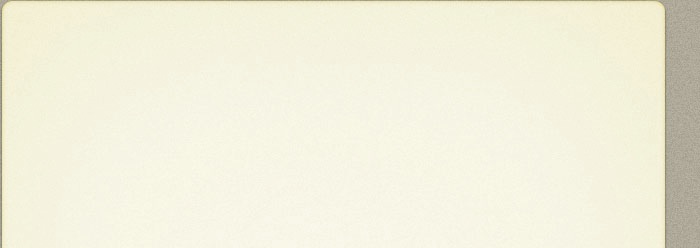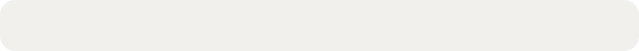前回,民法上の詐欺と刑法上の詐欺罪について説明しましたが,似たようなものに民法上の強迫(民法96条)と刑法の脅迫罪(刑法222条)があります。
ただ,こちらは読み方がどちらも「きょうはく」というだけで,漢字も違い,意味もかなり違います。
民法上の強迫は,詐欺と同じ条項に規定されているように主に契約の締結などの際の行為に関する規定です。
意味としては,相手方が自由な判断ができないくらい怖がらせて意思表示をさせることで,このようにして締結された契約などは詐欺の場合と同じく,取り消すことができます。
一方,刑法上の脅迫罪は人に害悪を加えることを告げて怖がらせる罪です。
意思表示と直接の関係は有りません。
害悪を加えることを告げ,怖がらせて契約を締結させたりする場合は,刑法223条の強要罪に当たりますが,強要罪は「義務のないこと」を行わせる場合全般ですので,契約締結などの意思表示だけとは限りません。
また脅迫して財物を交付させた場合は,恐喝罪(刑法249条)にあたりますので,「義務のないこと」が財物の交付である場合には,法定刑が3年以下の懲役である強要罪ではなく,法定刑が10年以下の懲役である恐喝罪にあたることになります。
なお恐喝罪については,被害者に支払などの義務があるときも成立するとされています。
それは権利の行使も裁判や強制執行などの法的手続によって行うべきだからです。
民法上の詐欺や強迫の規定は,取引などが自由な意思に基づいて行われるようにするための制度です。
刑法の詐欺罪や恐喝罪は相手方を勘違いさせたり怖がらせたりして財物を受け取ることを罰するための規定であり,脅迫罪は害悪を加えることを告げて他人を不当に怖がらせること,強要罪はその状態を利用して義務のないことをさせることを罰するための規定です。
民法と刑法の規定のどちらにも該当する場合もありますが,このように趣旨は異なります。